「片足レジデンス」
仕事から帰ってきて一番に目に留まるのは、オートロックの自動ドアを通ってすぐの大きな造花だ。引っ越してきて1ヵ月くらいまでは、花が出迎えてくれるなんてやっぱり東京の高いマンションは気が利いてる、とわくわくしていた。けれど人間なんて怖いもので、3か月すると、この造花は一体いつまで同じものを飾っているんだろう、と思ってくる。
ロビーに置かれた革のソファーと大きなガラステーブルは、川沿いの歩道からわざと見えるように置かれていて、デパートの女性用パウダールームの照明のように、白とオレンジの絶妙な照明で、きらめいて見えるようにつくられている。
自分の家のはずなのに、駅近くの安いスーパーのレジ袋がふくらはぎに当たって音を立てることくらいしか、現実味を感じなくなっているのはどういうことなんだろう、と思いながら愛美はエレベータのボタンを押してぼーっとした。
305の部屋の鍵を開け、電気をつける。パンプスを脱いでいると、スマホが鳴った。
あと30分くらいで着く、という光一からのメッセージに、ビーフストロガノフ作って待ってるね、と返事を書いた。
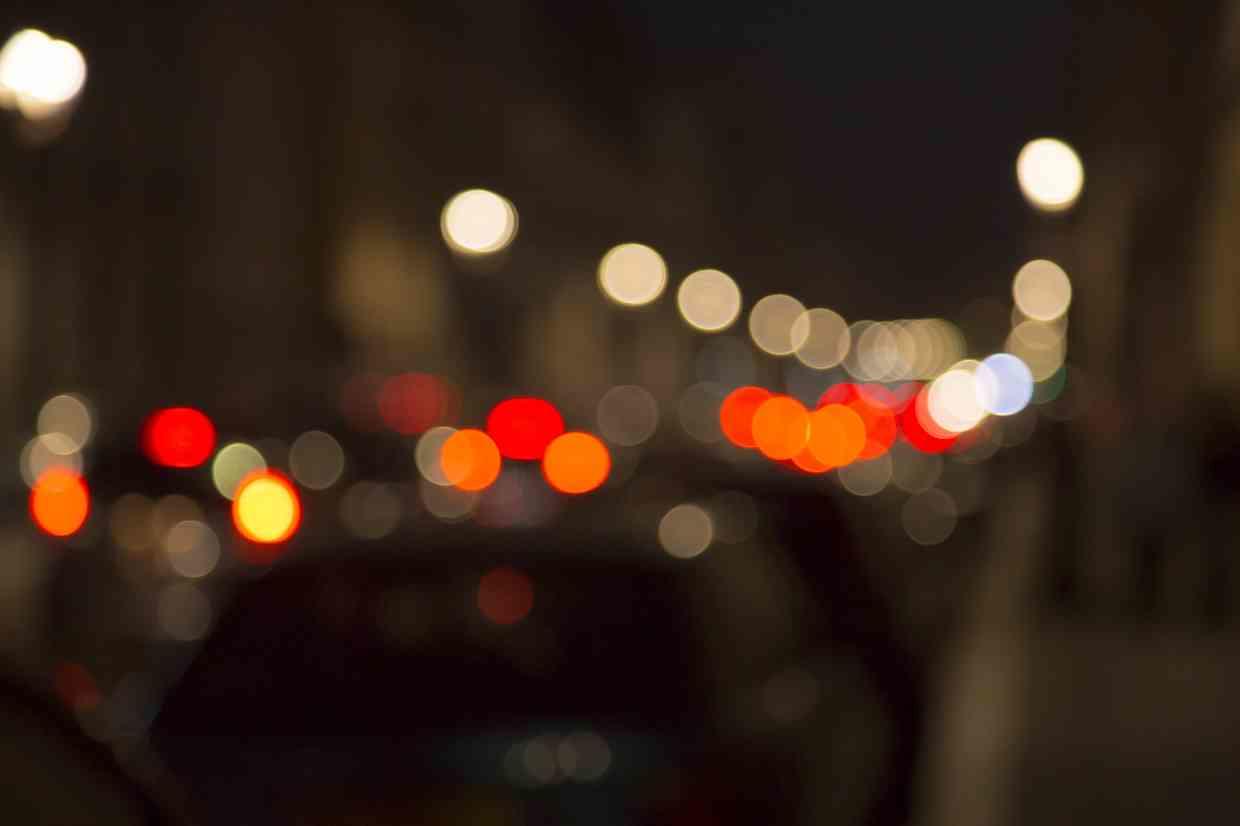
13畳の1Kには、白いテーブルとイス、オフホワイトの生地にワインレッドのストライプの柄で統一したベッドや枕、2人掛けのベージュのソファが置いてある。10階までは賃貸で同じ間取り、10階階以上はファミリー向けの賃貸か分譲でずっと広いはずだ。一人で暮らす愛美には十分すぎる広さで、家賃も15万で正直身の丈に合わないと思ったが、光一と一緒に過ごす時にはちょうどいいと感じていた。
スウェットに着替えてごろんごろんしたいなぁと思うのを抑えて、レジ袋から野菜と肉をごろごろと出した。床に転がった栄養ドリンクがゴンと音を立てて、やれやれと冷蔵庫に入れた。
玉ねぎをスライスしてきのこを食べやすい大きさに切る。根や皮はそのままディスポーサーのついたシンクに落としていく。これがなかったら光一に作る料理のほとんどが面倒になるだろうと毎回思う。
玉ねぎ、きのこに肉を加えて炒めつづけ、水を入れて弱火にした。作り置きのデミグラスにケチャップと醤油を足し、赤ワインを加える。あとはもう順調に煮えてくれたまえ、と、愛美はテレビをつけ、クッションを尻の下に敷いて床に座った。ソファーがあるのにどうしていつも床に座っちゃうんだろうな、と思う。
女優の交際報道を見ながら、心の中で、いいなぁ女優はなんでもありな感じで、とうらやむ。もし自分が女優になったらどんな部屋に住んでいるんだろう、と考えてみても、広すぎるリビングやベッドメイキングされた寝室が思い浮かぶだけで、そこにいるはずの自分は、どこかの雑誌で見たような、朝からココナッツオイルでパンケーキを焼いていそうな人物にはどうもなれない気がした。
インターフォンが鳴り、光一がひらひらと画面の向こうで手を振っている。自動ドアを開け、そのまま玄関の鍵も開けた。少しして部屋に来た光一は、いつもと変わらない調子で、すぐに、今日さぁー、と自分の話をはじめた。
へぇ、とか、ほぉ、とか返事をしながら、ガスの火をさらに少し弱めた。
「愛美疲れてるんじゃないの?」
テーブルにビールを置くと光一が言った。
「なんで?」
「なんでっていうか、なんとなく」
「忙しかったからかなぁ年度末だったし。でも家にいる時は落ち着いてるはずだよー」
「まぁな。この部屋居心地いいもんな」
それなら一緒に住もうとか、思わないんだろうか、と本音がよぎる。
「あんまり疲れためないようにしないとな、愛美は30超えてるんだし」
そう言って笑う光一がどれほど自分のことを考えてくれているのか分からない。愛美は33歳になり、光一は27歳になったばかりだ。
愛美はビーフストロガノフにブラックペッパーを入れながら、光一のほうこそ無理しないように、と返した。
「やっぱり? 分かる? そうなんだよー。なぁ、営業の森さんているっしょ?」
んー、と愛美は思い出せない顏を探した。部署が違うとさすがに覚えきれない。
「やらかしたんだよー。企業パンフレットの企画書作ったはいいけどさ、設立年違うわ理念違うわで、なにこれってなったわけ。で、聞いてみたら、2社やってて初校の戻りが同じ日で机に両方広げたもんだから何ページか入れ替えちゃってたんだとー」
あららら、と言いながら鍋からお皿にうつす。
「さすがに部長もカンカンでさぁ、あ、俺もね、俺もカンカンなわけよ」
そうだねぇ、と言いながら皿のビーフストロガノフに生クリームをかけ、ライスにはパセリをふりかける。テーブルにイタリアントマトのサラダと一緒に並べると、光一は、いただきまーす、と言って食べ、しゃべり、食べ、また、森がさ森が森がとしゃべり、食べた。
「ね、愛美、今日泊まっていっていい?」
「今日は泊まりたい気分なの? 実家はだいじょぶ?」
森が森が、というのと同じように、このあいだは親が親がと言っていた。帰らないと親が色々言ってくる、なんて大学生なの? と突っ込みたくなった。
「うん。いいじゃん、どうせ会社行くのも一緒なんだし」
いいよ、と笑顔で言うと、光一は、じゃあビールもう一杯、と空き缶を右手に掲げて言った。
このあとの流れはもう分かっている。自分が洗い物をしている間、バラエティ番組を見て、一緒にお風呂に入ろうと言いだしそうすればタオルに巻かれただけの姿でベッドに横たわる。短い愛撫はちょっと自分勝手で、ドラッグストアで光一が買った安い避妊具を使って抱かれ、けだるい空気の中で愛美がゆっくり話をしようとする頃には、この男子は眠そうに迷惑そうな顔をして眠ってしまうのだろう。
けど、怒ったりせずに、朝はバルミューダで焼いたパンを出したい。世界一おいしいパンが焼けるトースターだなんて気づきもしないんだろう。クロワッサン、フランスパンの種類で焼き方を選んで変えているのも気がつかないんだろう。なんでだろう、ちょっと前なら何も気づいてくれないようなところもかわいかった。
愛美は、空気入れ替えようかな、と言ってバルコニーを開ける。サンダルを履いて空を見ると、夏の星座がちゃんと見える。手すりによりかかるようにして下を見ると、マンション沿いの歩道で2人の女性が立っていて、一人が何度も頭を下げて謝っているように見えた。

風あったかいわ、と部屋に振り向くと、カレーをかきこむようにビーフストロガノフを食べている光一がいる。愛美は、それでいいんだろうか、いや、いいんだそれで、と思う。
自分のために働いて、自分のためにこのマンションに住んでいるのに、どうしてこんなに不安なんだろう。私はここで何をしようとしたのだろう。上京したときに理想としたものはもう手の中に全部あるはずなのに。それなのにこんなふうに、片足が部屋の中で、片足が屋外に放り出されている感じが今の愛美そのものな気がした。
お金持ちでもなければ貧乏でもない、歳ではないけど若くない、美人でないけどブスでもない、幸せなのに満足じゃない。
ねーどうしたのー、と光一がこっちを見て間延びした声で言う。
愛美は、なんでもないよーなんでもない、と返事をしながらドアを閉めた。









